※広告を利用しています
旦那さんから「海外赴任が決まった」と告げられると、見知らぬ国での新しい生活に不安を感じます。
特に小さなお子さんがいるなら「子どもも連れて帯同するか、それとも夫だけ単身赴任にするか」で悩むのが当然です。
わたしは2年ほど中国で、子どもたちが通う日本人向け学習塾で働いていました。
そこで海外在住の子どもに関するたくさんの相談を受けた経験は、わたしの財産になっています。
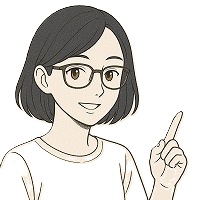
この記事はこんな方におすすめ!
・夫の海外赴任についていくか悩んでいる
・現地(中国)での駐在家族の生活をイメージしたい
・帯同した場合、子どもたちに負担がかからないか心配
この記事では、私が実際に見てきた駐在家族たちをもとに、帯同するかどうかで悩んでいる方が知っておきたい駐妻や子どもたちの日常、そして決断のヒントをお伝えします。
語学で悩んでいる方は、こちらも記事もどうぞ!
夫の海外赴任は単身?帯同?迷ったときの考え方
夫の海外赴任についていくか、単身で行ってもらうかは、「教育」「医療」「妻の適応」「夫の勤務」の4つを軸に、どこに優先順位を置くかで決まります。
正解は一つではないので、家庭ごとに最適な答えを出せばOKです。

心の中のモヤモヤは、現実を知って解決することもあります。
実際に渡航経験のある人の体験談が役立ちますよ!
身近に渡航経験者がいれば話を聞いてみましょう。
■判断のための主な軸
- 子どもの教育
小学生の場合、日本人学校を選ぶか、インターナショナルスクールを選ぶかで海外生活が大きく変わります。帰国後の学習や受験を見すえる家庭も多いです。 - 子どもの医療・生活
幼児は病気やケガが多く、現地の病院で言葉が通じるか心配になります。
医療環境をどこまでリサーチできるかが、帯同の安心材料になります。 - 妻の生活や適応力
現地で人と積極的に関われるタイプなら、コミュニティにも入りやすく生活も楽しめます。
反対に引っ込み思案だと、孤独を感じやすいです。
「自分は現地でやっていけそうか?」を考えてみて。 - 夫の勤務状況
夫が現地で忙しすぎる場合、帯同すると家庭の負担が妻に集中する可能性があります。
夫のサポート体制も、渡航前にしっかり確認しておきましょう。
海外赴任へ帯同する場合、どのような流れなのか知るのも大事!
海外渡航への準備4ステップをまとめた記事はこちらです。
中国で見た駐在家族|子ども・妻・夫の海外赴任中の様子
夫の海外赴任に帯同するか決めるには、現地に住んでいた人の体験談が有効です。
現実を知ると、「わたしにはムリ」「夫について行きたい」の判断をしやすくなります。
私は中国で2年間、日本人向けの塾講師として働き、数百人規模の駐在家庭の子どもたち(小学生~中学生)と接しました。仕事をしながら見えた駐在家庭の様子をお伝えします。
海外赴任先(中国)の子どもたちの様子
私が中国で塾講師だったとき教えていた駐在家庭の子ども達は、
日本人コミュニティーの中で生活しているせいか、日本と変わらない雰囲気でした。
当時、勤務先近くの日本人学校は生徒数800人以上。
そのうち約半数が塾に通っていました。
学校から塾、塾から家までは送迎バスで移動します。
子どもの一人歩きは、安全面を考えてほとんどありません。
面白かったのが、日本人学校・インターナショナルスクール・現地校それぞれの特色が、子どもに現れていた点です。
塾の休憩時間に洋書に読みふける女の子、困っている女の子に恥ずかしがらずサッと手を差し伸べられる男の子は、インターナショナルスクールの子でした。
インターナショナルスクールの子は少数派ですが教育熱心なご家庭が多く、中学受験を狙う子もチラホラ。
帰国子女向けの中学受験で作文を書かされる場合も多いのですが、
勉強ができるけれど作文や漢字が苦手な子が多く、国語の指導が大変でした。
日本人学校の子ども達は、ほぼ日本の小学生と変わりません。
現地でどのタイプの学校に通わせるかによって、子どもの成長も違いそうです。
妻(駐妻)の様子
塾の保護者面談や説明会では、駐在員の奥様方とお話しする機会がありました。
よく相談された内容は、子ども達が帰国後に日本の学校へスムーズに戻れるかどうかです。
「作文が苦手」「漢字を間違える」など国語の不安を口にされる方が目立ちました。
また、駐妻さんたちの生活スタイルは比較的アクティブな印象を受けました。
中国では当時、アイさん(家政婦さん)を比較的安く雇えたので、
家事や送迎を任せて趣味や友人関係に時間を使う奥様もいます。
保護者会にテニス帰りの姿で現れる方もいて、海外生活を満喫しているように感じました。
駐妻さんは積極的に外へ出て現地を楽しむタイプと、引っ込み思案で自宅中心に過ごすタイプに分かれます。駐妻の生活は、性格によって大きく違うのだと強く感じました。
積極的に外へ出て現地を楽しむなら、英語や現地語を少しでも学んでおくのがおすすめです。
\ 無料体験10日間以上! ![]() /
/
/ 体験の申込みはこちら! \
夫(駐在員)の生活と会社のサポート
保護者会のような集まりに来るのは母親が多かったですが、中学受験クラスの三者面談には熱心な父親がくることもありました。
中学受験に合わせて子どもと母親だけ日本に先に帰るケースも多く、自分自身が家族をどうサポートできるのか悩んでいる印象でした。
またわたし自身、海外で働いていましたが、会社は住む場所や通信機器、病院、両替などさまざまな面でサポートをしてくれました。日本人駐在員をサポートしてくれる現地に詳しい事務員がいると、相談しやすいと思います。
わたしが現地生活で楽しんだこと
わたしも「現地の言葉がわからない」「お金や医療は?」など不安でしたが、
実際はそれほど問題ではありませんでした。
海外生活はすごく楽しかったです。
中国では、次のことが印象に残っています。
- 寝台特急で一人旅
- 黄山を登る
- 中国人の友達と相互学習
- 変身写真
- 服、靴、メガネなどのオーダーメイド
- 不動産巡りをして気に入った物件に引っ越し など
たくさん経験したつもりでしたが、「もっといろいろやっておけばよかった」と後悔しています。
ただ、一人だから満喫できたのであって、小さな子どもがいると大変ではないかとも思います。
子ども連れ海外赴任の決断ポイント|教育・学校・子育て環境の不安
夫の海外赴任に帯同するか迷ったとき、特に小学生や未就学児など幼い子をがいる家庭では、教育環境や医療体制が整っているかが大きな判断材料になります。
また、海外生活に興味があっても子どもが小さいと躊躇するのもよくわかります。
ここでは、教育・学校・子育て環境の不安をまとめました。
どの学校に通う?日本人学校・インター・現地校の違い
帯同を考えている方の悩みのひとつが、現地での子どもの学校です。
選択肢は主に3つです。
- 日本人学校:日本の文部科学省の指導要領に準じた授業内容で、日本語・日本のカリキュラムを維持できます。帰国後もスムーズに公立・私立校に復帰できる点が魅力。
- インターナショナルスクール:多国籍な環境で英語や多文化に触れられる反面、授業料が高額で、帰国後に日本の教育内容とのギャップが生じる場合も。
- 現地校:現地語を学ぶチャンスは大きいですが、言葉や文化の壁があり、家庭でのサポートが欠かせません。
実際に中国で出会った駐在家庭の多くは、帰国後に日本の授業についていけるかを心配していて、日本人学校を選ぶケースがほとんどでした。
病気やケガに備えて|会社のサポート体制と現地医療をWチェック
小さな子どもを連れての海外生活では、体調を崩したときの対応が大きな不安要素です。特に小さな子どもは熱が出やすいので、お母さんは不安だと思います。
国によって医療レベルや診療スタイルが異なるため、「どんな病院に行けるのか」「言葉は通じるのか」を事前に確認しておきましょう。
駐在家庭では、会社経由で日本語対応の病院を紹介してもらえるケースが多いです。定期検診や予防接種を会社がサポートしてくれる場合もありますが、緊急時の対応や薬の違いに戸惑い、日本での治療を選ぶ家庭も少なくありません。
また、国によっては医療費が高額になるため、保険の補償範囲を確認し、24時間対応のクリニックや通訳サービスの有無を調べておくと安心です。
ワンオペ覚悟?生活サポート体制とママのキャパシティ
「海外生活=駐在妻の特権」と思われがちですが、実際にはサポートのないワンオペ育児になるケースも多いです。
夫は仕事で多忙、頼れる親族もおらず、言葉も文化も違う環境。
4歳と1歳の双子を連れていくような状況なら、想像以上の負担です。
子どもが熱を出したとき、買い物に行くにもタクシーを呼ぶ必要がある国もあります。
現地に日本人コミュニティやママ友ネットワークがあるか、ベビーシッターや家事代行を頼める環境かなど、サポート体制の有無が生活の質を左右します。
夫のサポートが得られないなら、妻のほうから「今は難しい、単身赴任をして」と正直に伝えるのも大切。
「行く」か「行かない」かの判断は、ママのキャパシティとサポート環境しだいといえるでしょう。
夫だけ海外に単身赴任するメリット・デメリット
夫が海外に赴任することになったとき、「家族も一緒に行くか」「単身で行ってもらうか」は、最初に悩む大きな分かれ道です。
小さな子どもがいたり、妻が仕事を続けていたりすると、「単身赴任のほうが現実的かもしれない」と感じる方も多いでしょう。
ここでは、夫が単身で海外に赴任する場合のメリット・デメリットを整理してみます。
夫だけ海外に単身赴任するメリット
- 家族の生活リズムや子どもの教育環境を変えずにすむ
- 親族や友人など、頼れる人が日本にいる安心感
- 妻が自分の仕事やキャリアを続けやすい
夫が単身で海外に赴任する場合、家族は日本でこれまで通りの生活を送れます。
子どもが受験期だったり、転校させたくなかったりする場合は、この選択がもっとも現実的です。
親や友人のサポートを受けながら、妻自身も仕事を続けたり、キャリアを途切れさせずにいられるという大きなメリットも。
海外生活に不安を感じる場合は、単身赴任という選択も「家族を守る形のひとつ」だと思います。
夫だけ海外に単身赴任するデメリット
- 夫婦で過ごす時間が減り、気持ちのすれ違いが起こりやすい
- 妻の負担が増え、ワンオペ育児になりがち
- 夫の健康管理や孤独へのケアが難しい
一方で、距離がある生活はやはり寂しさがつきものです。
連絡を取る時間が限られると、気持ちのすれ違いや心の距離も生まれやすくなります。
また、家のこと・子どものことをすべて一人で背負うのは、想像以上に大変。
夜中に子どもが熱を出しても、頼れる人がいないととても心細いはずです。
夫の側も慣れない海外での孤独やストレスを感じやすいため、お互いの近況をこまめに共有し合うことが大切です。
夫の海外赴任に帯同するメリット・デメリット
「せっかくの海外赴任、一緒に行ってみたい」そう思う気持ちは自然なことです。家族で過ごせる時間を大切にしたい、子どもにも海外経験をさせたい――そう考えるご家庭も少なくありません。
一方で、言葉や生活環境の違い、育児や仕事との両立など、現実的なハードルもたくさんあります。
ここでは、家族で帯同する場合のメリット・デメリットを見ていきましょう。
夫の海外赴任に帯同するメリット
- 家族そろって生活できる安心感がある
- 子どもが異文化や言語を自然に学べる
- 現地の生活や人との出会いが貴重な経験になる
家族で一緒に海外に行くと、一緒にいられる安心感は何よりの支えになります。
夫の仕事を間近で見られるのも、帯同ならではの経験。
子どもにとっては、言葉や文化の違いに触れるチャンスでもあります。
インターナショナルスクールなどに通えば、英語だけでなく多様な価値観を吸収できるのも魅力です。
妻自身も、海外での生活を通して世界が広がったり、新しい人との出会いがあったりするケースも多いです。
夫の海外赴任に帯同するデメリット
- 言葉や文化の違いに戸惑いやストレスを感じやすい
- 妻のキャリアが一時的に止まる可能性がある
- 小さな子どもがいると、生活全体が負担になりやすい
帯同には家族で一緒に過ごせるメリットがある反面、現地での生活に慣れるまでは苦労も多いです。
言葉が通じず、ちょっとした手続きや買い物にも時間がかかったり、病院探しで不安を感じたりします。
特に、小さな子どもを連れての帯同は、想像以上に体力も気力も必要。
夫が多忙で家を空けがちな場合、ワンオペ育児にりやすいです。
そして、妻のキャリアを中断せざるを得ない点も大きな悩み。
「帯同したい気持ちはあるけれど、戻ったときの再就職が不安」という声も多く聞きます。
【子どもの年齢別】帯同の向き不向きと親の負担
帯同するかどうかの判断は、家庭ごとの事情や子どもの年齢によって大きく変わります。
ここでは、年齢別の向き・不向きに加え、実際に先輩家庭がどのように判断したのかを紹介します。
未就学児の場合
未就学児は新しい環境への適応が早い一方で、親のサポートが欠かせません。
言葉の壁を気にせず友だちを作れる柔軟さがある反面、体調管理や生活リズムの調整が必要で、親の負担は最も大きい時期です。
現地の保育施設や幼稚園に入れる場合、言語が通じない・衛生面が気になる・送り迎えの方法がわからないなど、最初の数カ月は不安の連続。
また発熱やケガなどちょっとしたトラブルが多く、病院探しに苦労することがあります。
でも親が安心できる環境を整えられれば、幼少期の海外生活は異文化を自然に受け入れられる力を育てる大きなチャンス。
駐妻のサポート体制(夫の協力・現地の日本人コミュニティ・家政婦さんなど)をどれだけ確保できるかが、帯同判断のカギです。

わたしも2人の子育てをしているので、この時期が大変なのはよくわかります。
熱を出したら?子育て広場みたいなところはある?
悩みがあるなら、会社に現地在住の日本人を紹介してもらってもよいですね。
日本人に聞くのが難しいなら、現地に住む外国人に直接聞いてみるのもひとつの手です。
現地の人から言語を教わるPreplyのシステムなら、直接その国の人と話せますよ。
小学生の場合
小学生は言語の吸収力が高く、海外生活に最も順応しやすい時期です。
現地校やインターナショナルスクールに通えば、英語や現地語を自然に身につけ、国際的な視野を広げることができます。
一方で、日本語の読み書きや学習習慣が遅れがちになるリスクもあります。
日本人学校に通えばカリキュラムは日本と同じですが、塾や習い事の選択肢が限られる国では、家庭学習のサポートが必要になるでしょう。
この時期は「友達関係」が生活の中心になるため、学校選び=生活満足度に直結します。
どの学校が子どもの性格に合っているか、帰国後の進学をどう考えるかを事前に家族で話し合っておくと安心です。
中・高生の場合
中高生になると、進学や受験の時期と重なるため帯同の判断はより慎重になります。
海外で現地校やインターに通うと、日本の受験科目とずれるため、帰国後の受験準備が大きな負担になるケースも。
また、思春期の時期は友人関係やアイデンティティの形成にも敏感です。
急な環境変化や言葉の壁がストレスとなり、子ども本人が帯同を拒むケースも少なくありません。
その一方で、海外経験を通じて「自分の考えを言語化できる力」や「異文化理解力」を身につける子も多く、大学入試や将来のキャリアで強みになることもあります。
重要なのは、親が“経験としての価値”と“進学リスク”の両方を理解し、子どもの意思を尊重することです。

中国の日本人向けの塾では、日本の塾で使っているのと同じ教材を使って受験対策をしていました。受験準備が不安なら、塾に通って受験に備える方法も考えてみて。
夫の海外赴任に帯同するかで迷ったら|家族が笑顔でいられる選択を
海外赴任の形は、家庭の数だけあります。
夫婦が別々に暮らす単身赴任を選ぶ家庭もあれば、思い切って帯同する家庭もあります。
どちらが正解というわけではなく、家族みんなが笑顔で過ごせるかどうかがいちばん大切です。
海外生活には不安もありますが、いまはオンラインでいつでもつながれる時代です。
距離が離れていても、気持ちがつながっていれば「一緒に頑張っている」と感じられます。
逆に帯同を選ぶ場合も完璧を目指さないで、助けを借りながら暮らせばずっとラクです。
家族それぞれの年齢や性格、サポート環境によって、最適な形は変わります。
焦らないで自分たちの無理のない幸せを考えて、後悔しない決断をしましょう。
まとめ|夫の海外赴任は単身か帯同か?家庭に合った答えを
海外赴任の形は、家庭の数だけあります。
夫婦が別々に暮らす単身赴任を選ぶ家庭もあれば、思い切って帯同を決める家庭もあります。
どちらが正解というわけではなく、家族みんなが笑顔で過ごせるかどうかがいちばん大切です。
不安や迷いがあるときは、専門のサポートを利用してみるのもおすすめ。
赴任前に準備を整えておくことで、現地での生活もぐっと安心になります。
また、もしも海外赴任への帯同を決めたのなら、渡航前の準備も大切です。
こちらの記事では、出発前にやるべき4ステップをわかりやすくまとめています。
\ 無料体験10日間以上! ![]() /
/
/ 体験の申込みはこちら! \

当サイトはリンクフリーです。SNSやブログで紹介していただけるとうれしいです!








